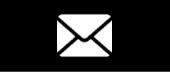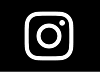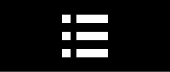自律神経失調症なら【脳の整体】大田区大森/蒲田/平和島
TEL. 070-9150-1059
平日10:00-19:00|土曜10:00-17:00|予約制
HALOカイロプラクティック☆平和島整体院
東京都大田区大森本町2丁目5−13
トライシブ大森本町1階
京急本線 平和島駅 東口徒歩1分
脳神経科学に基づいた
自律神経専門施術で
自律神経失調症を
短期改善・早期回復
自律神経失調症

最終更新日:
著者:HALOカイロプラクティック 院長 HARU M.D.
「自律神経失調症」とは名前の通り、自律神経の調整が失われる病気なのですが、医学的にはなぜ起こるのかハッキリと解明されていません。
元々、自律神経失調症とは1960年代に、本人には自覚症状があるのに検査をしてみても、検査結果から異常がみられず、なぜ症状がでるのかわからない不定愁訴に対して使われ始めました。
医者からすれば、診断がつかない症状につけることができる非常に都合の良い病名です。
「日本心身医学学会」では、自律神経失調症を 「検査をしても、その症状を裏付ける所見が見いだされず、また器質的病変がないのにさまざまな不定愁訴を訴える状態」として定義づけています。
また、心理的問題が精神症状として表れず、身体症状として表に出る自律神経失調症の一つに「身体表現性障害」があります。
身体表現性障害で現れる多い症状としては、「食欲もなく胃の不快感が続く」「めまい」「難聴」「喉の異物感」などです。
自律神経とは
自律神経とは、60兆を超える身体の細胞の働きを調整するために、全身に張り巡らされた神経です。
自分の意思とは関係なく、刺激や情報に反応して身体の機能をコントロールしています。逆に言えば、意識してもコントロールできないことを担当するのが「自律神経」です。
心臓も胃腸も、私たちが意識しなくても動きます。呼吸も意識せずに行っています。暑ければと自動的に汗をかきますし、寒ければと体温を一定に保とうとします。血液や代謝、体温調整なども含め、私たちの生命活動の根幹を24時間365日コントロールしているものが自律神経です。
そもそも、自律神経とは身体を活発にする交感神経(活動する神経)と、身体を休ませる副交感神経(休む神経)の2種類の神経から成り立っています。

交感神経は、エネルギーを消費するような働きがあり、心臓の鼓動や血圧を高めたり、感情の変化などの精神活動を活発にします。
一方、副交感神経は、エネルギーを蓄えたり回復させるような働きがあり、消化器官の働きを活発にしたり、リラックスや睡眠、休息をとるときに優位に働きます。
したがって、たとえば、交感神経が優位になると、緊張したり、なかなか寝つけなかったりします。逆に、副交感神経が優位になると、いくら寝ても寝たりないといったようになります。
眠っている時に呼吸する、血液を流す、胃で食べ物を消化する、腸で栄養を吸収する、老廃物や疲労物質を集めて便や尿で排泄するなどの動きも、すべて自律神経によるものです。
自律神経は、この2つの神経がバランスよく自動的に切り替わるようになっています。
自律神経との三角関係
自律神経が乱れる(交感神経と副交感神経の切り替えが上手くいかない)と起きる厄介な問題は、免疫(白血球のシステム)やホルモン分泌(代謝エネルギーのシステム)も、自律神経に連動して乱れてしまうことです。

自律神経も免疫系もホルモン分泌系も、うまくバランスをとり相互に作用しあっているから、健康が保たれるのです。
もし、自律神経が乱れると、ホルモン分泌の調整できず、代謝や成長、生理機能に影響がでたり、免疫の調整ができず、病気にかかりやすくなります。
逆に、免疫やホルモン分泌に異常が起これば当然、自律神経にも異常が起きます。
自律神経失調症の4タイプ
自律神経失調症には大きく分けて4つのタイプがあります。
本態性型自律神経失調症
生まれつき自律神経の調整機能が乱れやすい体質の人、低血圧や虚弱体質な人、立ちくらみしやすい人に見られるタイプ。
神経症型自律神経失調症
性格的、心理的な要因によって自律神経の機能に不調をきたし、不定愁訴の症状が現れるタイプ。自分の身体の変調に敏感で、心配性で些細なことにもこだわる人、不安感が強い人、気にしやすい人に多く見られます。
心身症型自律神経失調症
自律神経失調症のほぼ半数がこのタイプ。喜怒哀楽の感情や疲労などのストレスを無理に抑えることにより、自律神経に変調をきたします。真面目で頑張りすぎてしまう人、自分に厳しい人、ストレスに弱い人、強いストレスを長期間受けている人に発症しやすいです。
抑うつ型自律神経失調症
ストレスが慢性化し、蓄積され鬱状態になり、体に変調をきたします。几帳面、完全主義、執着心が強い、気分が沈みやすいなどの傾向にある人に見られます。
様々な症状

自律神経は体のすべての器官に関連しています。ですから、心臓、血管、呼吸器系、消化器系、皮膚、生殖器系、関節、精神に至るまで、ありとあらゆるところが網羅されます。
大きな括りでは、更年期障害、起立性調節障害、パニック症/不安障害、片頭痛、メニエール病、気管支喘息、副腎疲労症候群…等々も、自律神経失調症の一つです。
男性よりも、生理、妊娠、出産、授乳、閉経などを経験する女性の方がホルモンバランスが乱れやすいため、自律神経失調症になりやすいようです。また、個人差も大きい上、性格、体質、気分にも影響されます。
各器官に現れる症状としては…
目の疲れ、涙目、目の乾き、かすみ目、目の奥が痛い、耳鳴り、耳の閉塞感、口の感覚異常、味覚異常、顎関節症、口の渇き異物感、喉の閉塞感や圧迫感、喉のイガイガ感、喉の痛みや乾き、喉の奥が詰まった感じ、喉のムズムズ感、ヒステリー球
手や腕の痺れや痛み、握力低下、冷え、ほてり、感覚が鈍くなる
生殖器官なら、勃起不全、射精不能、生理不順、陰部のかゆみ
筋肉や関節なら、肩こり、張り、痛み、筋肉痛、胸痛、背中や腰の緊張感、関節の怠さ、力が入らない
頭痛、頭重感、薄毛(脱毛)片頭痛の併発
呼吸器官に現れると、咳、痰、息苦しさ、息が詰まる、息が吸えない、息切れ、酸欠感、過換気症候群(過呼吸)の併発、気管支喘息の併発
心臓血管なら、動悸、息切れ、胸の圧迫や痛み、胸やけ、高血圧・低血圧、鼻血、貧血、不整脈の併発
皮膚関連では、多汗、冷や汗、汗がでない、過剰な脇汗、乾燥、かゆみ、寒気
消化器官関連では、吐き気(嘔吐)、胃もたれ、膨満感、便秘、下痢、胃痛、腹痛、過敏性腸症候群の併発、胃潰瘍・十二指腸潰瘍の併発、食道の詰まり感、下腹部のはり、ガス溜り
泌尿器官では、頻尿、残尿感、排尿痛、血便、血尿
脚や足なら、しびれ、痛み、冷え、ふらつき、ほてり
全身症状としては、疲労感、疲れやすい、倦怠感、微熱、ほてり、冷え、めまい、ふらつき、立ちくらみ、睡眠障害、食欲不振、アトピー、低体温、乗り物酔い、メニエール病の併発、発熱・微熱、震え、全身の痛み
精神症状では、不安感、恐怖心、怒りっぽい、イライラ、無気力、集中力低下、記憶力低下、注意力低下、情緒不安定、気が滅入る、鬱病の併発
…上記以外にもまだまだあります。
高血圧・高脂血症・糖尿病
研究データによると、高血圧や高脂血症、糖尿病などを患っている人の自律神経を測定すると、対象となった患者全員において、自律神経の交感神経が過剰に活発状態になっていることがわかっています。
つまり、自律神経が乱れており、当然ながら、免疫力も低下しているわけです。
高血圧や高脂血症、糖尿病患者に対する病院での現在の主な治療は、投薬と生活習慣の改善です。しかし、投薬はあくまで対処療法であるため、生活習慣の改善がとても大切になります。そして、生活習慣の改善の主目的は、自律神経のバランスを整えることです。
交感神経が過剰に優位になっている状態を改善するには、交感神経を制御し、副交感神経を活発にする形が望まれます。副交感神経と交感神経の活動割合が整うと、身体の隅々まで血液、栄養、酸素などが行き渡り、全身の細胞や臓器が元気になり、免疫力も上がるため、病状は格段に回復します。
高血圧、高脂血症、糖尿病に限らず、多くの病気を患っている人は、病院で処方される薬に頼りがちですが、薬の効果は生活習慣の改善、つまり自律神経バランスの改善があって初めて効果が望めるものだということを理解する必要があると思います。
高血圧、高脂血症、糖尿病などは、食生活を見直すことも大切ですが、自律神経の副交感神経のレベルを上げることができれば、必ず改善が見込める病気なのです。
主な原因

現代社会における最も多い原因として、「精神的あるいは身体的なストレス」が挙げられます。
ストレスがかかると、自律神経の交感神経が影響を受けます。交感神経が刺激されると、血圧が上がってしまい、動悸がして、食欲が落ちます。この状態を「交感神経の緊張」と呼びます。
交感神経の緊張が続くと、身体は疲労を感じ始め、身体がオーバーヒート状態になって粘膜や体内組織に障害が起き、体調不良から病気へと発展してしまうことになります。
また、交感神経が刺激され身体に負担がかかり過ぎると、身体は防御反応を起こし、身体を守ろう働きます。つまり、交感神経とは反対の副交感神経が働き始めます。
ただこの時、副交感神経が働き過ぎてしまうことが多々あり、怠くてやる気が出ない状態になったり、ふさぎ込んだりするような状態を引き起こしてしまいます。これを「副交感神経の過剰反応」と呼びます。
アレルギー性疾患、痛み、腫れ、発熱、咳、下痢、吐気なども、この副交感神経の過剰反応によるものだと言われています。
ストレスにより「交感神経の緊張」あるいは「副交感神経の過剰反応」が続くと、体調を崩し「自律神経失調症」と呼ばれる病気になってしまうのです。
免疫系の異常
自律神経は免疫系やホルモン分泌もコントロールしています。したがって、免疫系あるいはホルモン分泌に異常が出れば、それらを制御している自律神経にも異常が現れます。
免疫をコントロールしているということは、白血球をコントロールしていることになります。
したがって、ストレスにより自律神経が乱れると、免疫力にも影響し、風邪をひきやすくなったり、感染症や様々な病気にもかかりやすくなるわけです。
白血球の大半を占めるのが「顆粒球」と「リンパ球」です。もし、強いストレスを受け「交感神経の緊張」状態になると、白血球中の顆粒球の割合が増えます。
顆粒球が増え過ぎると活性酸素が発生し、胃や腸の粘膜をチクチク攻撃するようになります。つまり、顆粒球が増えることは、腸にとって望ましいことではないのです。最悪の場合、「胃潰瘍」に発展してしまいます。
逆に「副交感神経の過剰反応」状態になると、リンパ球が増え過ぎ、アレルギー物質などの抗原に対して敏感に反応し始めてしまいます。「帯状疱疹」などもこの状態といえます。
ちなみに、近年、子供や若い成人のアレルギーが増加傾向にありますが、その原因の一つは、お菓子やジュースなど甘い物の摂り過ぎにあります。甘い物を摂りすぎると、消化を促進するために副交感神経が常に優位になり、リンパ球が増え過ぎた結果、アレルギーを引き起こすとも考えられています。
受診する診療科

病院に行き「自律神経失調症」と診断された後、多くの場合は「心療内科」への受診を勧められるはずです。
では、心療内科と精神科の違いは?
『心療内科』では、ストレスや心理的な問題が関わっている「身体的な病気や症状を対象にしており、心身の両面からアプローチ」していくことになります。したがって、自律神経失調症や心身症など、ストレス性身体疾患の場合は心療内科になります。
一方、『精神科』の場合は、その名前のとおり、鬱病や不安障害、統合失調症など精神疾患を対象に、薬物療法や心理療法によってアプローチすることになります。
ただ、ストレス性身体疾患であっても、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、過敏性腸症候群、メニエール病などのような症状は、内科や耳鼻科、循環器科、消化器内科といった一般科を受診することになる場合が多いです。
メンタルクリニックの場合は、心療内科と精神科を兼ねているところも多いようです。
病院検査と治療薬

最も身近な身体の調子を知らせるバイタルサインとして、「血圧」があります。静かに横になって血圧を測り、その後、立ち上がった状態で10分間、1分ごとに測定します。
血圧検査でわかる自律神経の異常は、2つのパターンに分けられます。
1)最高血圧が「21mmHg」以上下がり、最低血圧も「16mmHg」以上下がる場合、立ちくらみ、目眩などの起立性低血圧症状を起こしやすい。
2)最高血圧は下がるが、最低血圧は上がって血圧の差が縮まる場合、手足の静脈還流(心臓に戻る血液の流れ)が不十分なために起こっている可能性があり。脱力感が強い、疲れやすいなどの症状が現れやすい。
血圧検査において最高血圧と最低血圧の差が縮まる人には、同時に脈拍数の増加もみられます。
また、深呼吸をゆっくりと繰り返し、息を吸ったときに脈拍数が増加し、吐いた時に減少するという呼吸性不整脈がでることもあります。これは、副交感神経系の働きが強くなる自律神経失調症に特徴的なものです。
その他、皮膚を軽く引っかいて痒みが広がるかをみることもあります。健康な人でも、爪やスプーンの先で胸や背中の皮膚を引っかくと、すぐに白い筋が浮き上がってきますが、これは正常な反射でしばらくすると消えます。
一方、自律神経失調症の傾向があると、引っかいた部分が大きく盛り上がり、じんましんのような痒みが生じたり、なかなか浮き出た筋が消えず、他の部分にまで痒みが広がることがあります。この症状は「皮膚紋画症」と呼ばれ、副交感神経優位の自律神経失調症の人に多く見られます。
心臓の働きを検査(心電図)することもあります。横になった状態で心電図をとり、立ってから3~7分後にもう一度記録します。自律神経失調症の状態では、血管の運動神経や心臓の洞調律の動きが低下しているため、心電図の波形の乱れが見られます。
基礎体温でも自律神経失調症の診断ができることもあります。特に女性の場合、月経周期、月経量、月経前症候群(PMS)や月経困難症などの症状は、自律神経機能に多く影響されます。したがって、女性は基礎体温が非常に重要な手がかりになることがあります。
正常な基礎体温は、月経の1日目から低温期が約2週間続き、排卵で最も体温が下がったのち、約2週間の高温期に入るサイクルを繰り返します。ちなみに、更年期障害の場合、ホルモンの分泌障害があるのは45パーセント程度です。
心理テストなども行うこともあります。そして、総合的に評価してその人に適して治療方針が決められます。

自律神経調節薬
① 交感神経の興奮によって血管が収縮して起こる症状には、グランダキシン(一般名:トフィソパム)
② 更年期に起こる症状には、ハイゼット、ガンマー・オーゼット(一般名:ガンマ・オリザノール)
※ 副作用は、眠気、吐き気、ふらつき、食欲不振、めまい など。
自律神経末梢作用薬
① 動悸や不整脈などの循環器症状には、β(ベータ)ブロッカー:インデラル(一般名:プロプラノロール)
② 下痢などの腹部症状には、副交感神経遮断薬:ブスコパン(一般名:臭化ブチルスコポラミン)
③ 低血圧や立ちくらみなどの症状には、交感神経興奮薬:リズミック(一般名:メチル硫酸アメジニウム)、エホチール(一般名:塩酸エチレフリン)、メトリジン(一般名:塩酸ミドドリン)
※ 副作用は、血圧が下がる、徐脈、呼吸困難、目の調節不全、眠気、ふらつき、食欲不振、動悸 など。
もし、自律神経失調症で不安が伴う場合は次のような薬が合わせて処方されることもあります。
抗不安薬(精神安定剤)
(商品名:リーゼ、デパス、レキソタン、セディール、ソラナックス、ワイパックス、セレナール、セルシン、ホリゾン、コントロール、バランス、メレックス、セパゾン、レスミット、メイラックス、レスタスなど)
※ 副作用は、眠気、ふらつき、倦怠感、脱力感、集中力低下、めまい、頭痛、かすみ目、喉の渇き など。
抗うつ薬
(商品名:デプロメール、パキシル、ジェイゾロフト、レクサプロ、トレドミン、サインバルタ、リフレックス、レメロン、トフラニール、トリプタノールなど)
※ 副作用は、吐き気、眠気、便秘、頭痛、口の渇き、食欲増加、排尿障害、頻脈 など。
※ 留意すべき点
抗不安薬や抗うつ薬には、不安や心身の緊張をほぐし、自律神経を安定させる働きがあります。
自律神経失調症が長く続くと、症状に対する不安やこだわり、様々なストレスが心身の緊張を招き、その緊張が症状を悪化させ、ますます不安が強くなるという悪循環が起きることが少なくありません。
そのような悪循環を断ち切るために、抗不安薬で不安を取り除き、心身のリラックスを図って症状が悪化するのを防ぐこともあります。
ただし、抗不安薬は、不安があるとすぐに服用したくなるといった「薬に依存してしまう傾向」を招く副作用があるとも言われます。
一方、急に服用を中止すると、イライラや不安、震え、不眠などの離脱症状が現れることもあるようです。
睡眠薬
(商品名:ハルシオン、アモパン、マイスリー、ルネスタ、ロピレム、レンドルミン、リスミー、ロヒプノール、サイレース、ネルボン、ベンザリン、エリミン、ベルソムラ、インスミン、ダルメート、ドラールなど)
※ 副作用は、眠気、ふらつき、めまい、物忘れ など
ただし、睡眠薬や睡眠導入剤などは不眠を治すというものではなく、眠れないなら薬の力で眠らせてあげましょう…といった役割の薬です。麻酔のようなものとお考え下さい。
漢方薬
■ 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとおう)
体格がよく、比較的体力がある人。不眠、不安、イライラなどの精神症状があり、便秘気味、頭痛、頭重、肩こりがある場合に適応。
■ 桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)
虚弱体質で痩せて顔色が悪い人。不安やイライラなどの精神症状や手足の冷え、のぼせ、動悸がある場合に適応。
■ 加味逍遥散(かみしょうようさん)
虚弱体質で疲れやすい人。不安、不眠、イライラなどの精神症状が強く、肩こり、頭痛、めまい、上半身が熱くなるのぼせ、ほてり、発汗がある場合に適応。
■ 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
体格がしっかりしていて、多くは赤ら顔の人。月経不順、冷え性、頭痛、めまい、のぼせなどがある場合に適応。
■ 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
顔色が優れず、神経質で疲れやすく、冷え性の人。喉がつまった感じ、動悸、むくみ、呼吸困難感、咳、胸痛、めまい、吐気がある場合に適応。
■ 抑肝散加陳皮半夏湯(よくかんさんかちんぴはんげとう)
体力が低下した人。神経過敏で興奮しやすい、怒りやすい、イライラする、不眠などの精神症状が強い場合に適応。
■ 加味帰脾湯(かみきひとう)
体力が低下し、顔色が悪い人。貧血、不安、動悸、不眠、食欲不振、微熱、胸苦しさがある場合に適応。
■ 柴朴湯(さいぼくとう)
体力が中程度の人。気分がふさぐ、喉や食道に異物感がある、動悸、めまい、吐気などがある場合に適応。
■ 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
虚弱体質で胃腸が弱い人。食欲不振、疲労倦怠、たくさん汗をかくなどの場合に適応。
■ これら漢方薬の副作用
頭痛、肩こり、めまい、ほてり、のぼせ、不眠、イライラ、不安、抑うつ、動悸、便秘、冷え、耳鳴り、腹痛、月経不順、倦怠感、不安、食欲不振、喉の閉塞感、食道の異物感、立ちくらみ、膨満感、頻尿、目の疲れ、吐き気など
危険な薬の常用

薬の常用は、交感神経の過剰な緊張を維持させてしまうため、血流が抑制され、体温低下が続き、免疫力の低下を招きます。病気が治りにくくなるわけです。
血圧を下げる降圧剤や上げる昇圧剤などは、薬の効果が効いているときは良いのですが、朝など効果が切れたときは抑圧された状態から血流が一気に解放されるため、状態が悪い状態へ戻ってしまいます。
降圧剤、昇圧剤、利用剤、消炎鎮痛剤、免疫抑制剤、抗不安剤、精神安定剤、ステロイド剤、抗生物質、、、等々、薬を服用する期間が長いほど、もともとの病気を治りにくくし、新たな病気の引き金にもなってしまいます。
睡眠薬も同様です。睡眠薬は、交感神経を興奮させて感覚を麻痺させ、意識を消失させて眠りにつかせる(気絶させているようなもの)といった、一種の麻薬のようなものです。毎日飲み続けているうちに、白血球の顆粒球が増えて脈が速くなり、顔色が悪くなってきます。
進行してしまうと、睡眠薬の量を増やさないと効かなくなり、ますます精神的にも追い込まれます。
睡眠薬による熟睡は、いわば気絶しているようなものであり、本来の副交感神経優位になって眠るといった自然の形とは違います。
薬依存の悪循環を断ち切る勇気も必要です。もちろん、薬で症状を抑える必要があるときもありますが、薬がもたらす影響(交感神経の緊張と免疫力の低下)を忘れず、早めに薬から離れることも大切です。
HALOカイロプラクティックでは
HALOカイロプラクティック☆平和島整体院では、自律神経失調症で悩む多くの方の健康を回復させてきています。
そもそもの原因がストレスにあることが多いため、最終的にはストレスを排除しなければなりませんが、ストレスを排除する元気や意欲を取り戻すためにも、まずは崩れてしまった自律神経バランスを回復させる必要があります。
自律神経は脳の奥、中心に位置する「視床下部」というところで、無意識下にコントロールされています。そして、様々なホルモン分泌に関わっている「下垂体」が視床下部の下側につながっています。
つまり、自律神経系やホルモン分泌系がかかわる症状に関しては、少なくともこの「視床下部」「下垂体」を調整することが必要になってくるのです。
自律神経失調症は、短期改善・早期回復を目指す【脳の整体】の適応になります。施術回数は、週一回×3ヵ月程度になります。
自律神経失調症でどこに行っても埒があかないとお悩みなら、是非、自律神経失調症や起立性調節障害を専門とするHALOカイロプラクティック☆平和島整体院へお越しください。
呼吸を意識して!

自律神経は自分の意思ではコントロールできない神経ですが、呼吸の仕方によってはある程度コントロールできると言われます。
息を吸う(吸気)ときに交感神経が優位になり、息を吐く(呼気)ときに副交感神経が優位になります。
また、口での呼吸は浅い呼吸になるため交感神経が活発になり、鼻での呼吸は深いゆっくりとした呼吸になるため副交感神経が活発になります。
例えば、ストレスで胃がキリキリ痛いような場合は、身体の免疫力を高めるためには副交感神経を優位にする必要があり、鼻呼吸の呼気に重点を置くと良いわけです。
最近の子供や若い人達を外で見かけると、意外なほど皆、口が半開き状態なことに気づきます。これは無意識のうちに口で呼吸しているからです。つまり、交感神経が優位な状態の人がとても多く、免疫力が低い傾向にあるわけです。
口呼吸が習慣になってしまうと寝ている時も当然口で呼吸しており、吸い込んだ空気が直接喉にあたることは、喉の器官を冷却してしまい喉の痛みにつながります。また、細菌が体内に侵入しやすい状況になってしまいます。
したがって、免疫力を下げないためにも、意識して鼻呼吸することをお勧めします。
鼻呼吸の習慣がつけば、次に意識することは、腹式呼吸か胸式呼吸かです。腹式呼吸の場合、吸気でお腹が膨れ、呼気でお腹がへこみます。胸式呼吸の場合、吸気で胸(肋骨)が膨らみ、呼気で胸(肋骨)が縮みます。
この腹式、胸式呼吸の違いですが、腹式呼吸をすると副交感神経に働きかけて精神を穏やかにする作用があり、胸式呼吸をすると交感神経に働きかけてエネルギーを満たす作用があります。
したがって、免疫力を上げたい人や精神を安定させたい人は、腹式呼吸を意識した方が良いです。元気を出したい人は胸式呼吸がお勧めです。
自律神経を整える食事を!

自律神経失調症に悩んでいる人は、ストレスに満ちた環境下にいることが多く、ビタミン「B群」や「C」の消費が増えることがわかっています。
ビタミンB群の摂取は、神経の働きを正常に保つために欠かせません。
B1が不足すると、身体の怠さや疲れやすさの他、脳のエネルギーが不足してイライラしたり怒りっぽくなったりします。
B6が不足すると、気分の落ち込み、ふさぎ込みなどが見られることがあります。
B12が不足すると、息切れ、手足の痺れ、気分の不安定さなどの原因となります。
ビタミンCは、ストレスに対抗するコルチゾールの合成にかかわります。人がストレスを受けた時、副腎皮質からコルチゾールが分泌されますが、これはビタミンCやコレステロールから作られます。このように、ストレスの多い人ほど、ビタミン類を不足させないことが大切です。
ちなみに、適度なコレステロールは身体の細胞やホルモンの材料となる大切な栄養素の一つです。
カルシウムやマグネシウム、タンパク質の不足も、動悸や息苦しさ、胸の圧迫感、妙にイライラしたり、すぐ怒りっぽくなったり、、、など、精神不安につながる原因になります。
乳酸菌の摂取も大切
もし、毎日あなたが便秘気味なのであれば、是非、乳酸菌をたくさん摂取して腸内細菌を整えてください。
腸には、輪状筋と縦走筋という二つの筋肉があり、その筋肉が収縮を繰り返す「蠕動(ぜんどう)運動」をするこで、内容物を移動させます。
この蠕動運動をコントロールしているのが、自律神経なのです。
自律神経のバランスが良い人は腸の状態が良く、また、腸の状態が良い人は自律神経が整いやすいと言えます。
便秘が続くと、疲れやすく体調が悪くなったり、イライラしやすくなったり、怒りっぽくなったり、ひどい場合は睡眠不足にもなります。
ちなみに、朝起きたらまず「コップ一杯の水」を飲むのも、副交感神経を刺激し胃腸の蠕動運動を促すのに良いと言われています。